どうも、TAKE SKYのたけです。
今回は、「空港に着陸できなくて引き返す事態」や
「欠航」が頻繁に起こる空港と、
滅多なことでは「着陸できない事態」や
「欠航」にならない空港の違いは何かに迫ってみます。
皆さんが飛行機で旅行や出張などで、
ある程度大きな空港に向かう場合は、
殆ど予期せぬ事態は起こらないけれども、
離島の空港や小さな空港に向かう便で、
「天候が悪く着陸ができない為、出発地に引き返します」
みたいな事になった方もいらっしゃると思います。
天候が悪いとか視界が悪いと言っても、
なぜ羽田や大阪では着陸できるのに、
小さな空港は着陸できない場合があるのか?
そんな疑問に解説していきます。
まず大雑把に説明すると、
計器着陸装置が設置されているか、いないかが理由!
例えば視界が悪い場合、この計器着陸装置が設置されていれば
パイロットは滑走路がある程度見えなくても、
計器のみで着陸できます。(条件はあります)
しかし、この装置が設置されていない空港では、
パイロットはある地点から滑走路が視認できなければ
着陸することができません。
これがほとんどの原因です。
ただ、計器着陸装置が付いているからと言っても、
100%着陸できるわけではありません。
その条件を解説します。
計器着陸装置による着陸の条件
計器着陸装置のカテゴリー(精度)の分類
※決心高 (着陸を判断する高度)
※滑走路視距離 (着陸を判断する場合の滑走路の視認距離)
| カテゴリー | 決心高 | 滑走路視距離 |
|---|---|---|
| カテゴリーI (CAT I) | 200ft以上 | 550m (1800ft) 以上または視程800m以上 |
| カテゴリーII (CAT II) | 100ft以上200ft未満 | 300m (1200ft) 以上 |
| カテゴリーIIIA (CAT IIIA) | 100ft未満または設定なし | 175m (700ft) 以上 |
| カテゴリーIIIB (CAT IIIB) | 50ft未満または設定なし | 50m (150ft) 以上、175m (700ft) 未満 |
※ ただし、航空機側もCATⅢに対応した装置が搭載されていなければなりません。
高カテゴリーが設置されている空港
カテゴリーⅢ (CAT Ⅲ) ILS設置航空
● 東京国際空港 (羽田空港) Rwy34R
● 成田国際空港 Rwy16R
● 中部国際空港 (セントレア) Rwy36
● 新千歳空港 Rwy19R
● 釧路空港 Rwy17
● 青森空港 Rwy24
● 広島空港 Rwy10
● 熊本空港 Rwy07
カテゴリーⅡ (CAT Ⅱ) ILS設置空港
● 東京国際空港 (羽田空港) Rwy34R
● 成田国際空港 Rwy16R
● 中部国際空港 (セントレア) Rwy18
● 新千歳空港 Rwy19R
● 関西国際空港 Rwy06L / R Rwy24L / R
● 熊本空港 Rwy07
いかがでしょうか?
天候が悪い場合、
着陸できる空港とできない空港の違いは
理解していただけたでしょうか?
ただし、いくら計器着陸装置が設置してあっても、
風が規定値を超えている、
気流の問題などで着陸できない場合もあります。
それは大空港も同じです。
もし着陸不可能で折り返しになったり、
他の空港に変更になっても、
お客さんの安全を第一に考えての対策です。
もしも、この様な場合に遭遇したら、
焦りますが、この事を思い出して理解しましょう。
今回もTAKE SKYをご覧頂き、ありがとうございました。
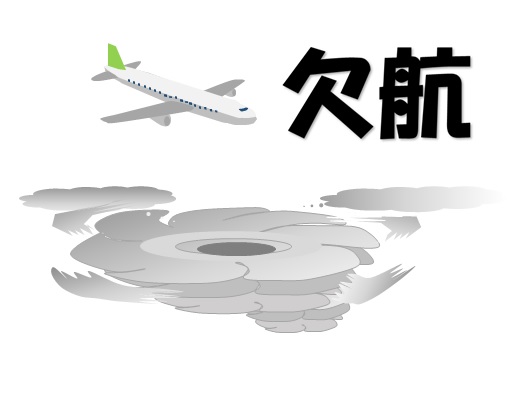
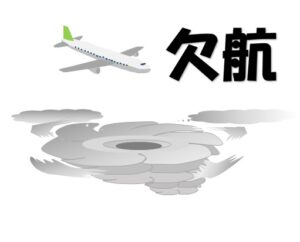


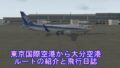
コメント